現代人にとって「質の良い睡眠」を取ることは、健康維持のために非常に大切なことですよね。 睡眠は、私た…
昭和初期の三銭、現在の価値はいくら?「アンパン」から紐解く歴史と経済
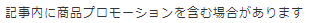

NHKの朝ドラ「アンパン」を見ていたとき、印象的なシーンに出会いました。アンパンを三銭で売ろうとした主人公が、周囲の人々から「高い!」と言われてしまう場面です。
現代の感覚で考えると、三銭がもし50円~100円程度なら「安いじゃないか」と思うのに、なぜ当時の人々はそう感じなかったのか?

今回はこの疑問をきっかけに、昭和初期(1926年~1930年代前半)の三銭が現在の価値でいくらになるのかを、物価や給与、生活文化の視点から徹底的に調べてみます。
ドラマの背景や当時の社会状況にも目を向け、歴史的な深みと現代とのつながりを探り、三銭が映し出す昭和初期の暮らしや価値観に迫ります。
この記事でわかること
- 三銭の現在の価値(150~200円)
- 物価と給与から見た三銭の重み
- 「アンパン」で三銭が「高い」と言われた理由
- 昭和初期の庶民の暮らしと文化
- 三銭から見える当時の社会状況
- 現代との感覚の違い
「昭和初期の三銭」はいくら?現在の150~200円か
1. 三銭の価値を物価から紐解く
まず基本的なアプローチとして、当時の物価と現代の物価を比較し、三銭の価値を算出してみます。

昭和初期の物価データは限られていますが、歴史書や資料から代表的な品目の価格を拾ってみると、次のようになります。
- 米1kg:20~30銭(地域や年による変動あり)
- 立ち食いそば:5~10銭
- 新聞1部:1~2銭
- 駄菓子:1銭程度
- 電車賃(初乗り):5銭前後
一方、2025年4月時点の日本の物価を基準にすると
- 米1kg:400~500円(スーパーの一般価格)
- 立ち食いそば:300~500円
- 新聞1部:150~200円(朝刊単価)
- 駄菓子:10~50円
- 電車賃(初乗り):150~200円(都市部)
米を基準にした計算
米は当時も今も生活の基本。昭和初期の米1kgを25銭、現代を450円と仮定すると
- 1銭の価値 = 450円 ÷ 25 = 18円
- 三銭 = 18円 × 3 = 54円
そばを基準にした計算
街角の立ち食いそばは庶民の味。7銭が400円に相当すると仮定
- 1銭の価値 = 400円 ÷ 7 = 約57円
- 三銭 = 57円 × 3 = 約171円
新聞を基準にした計算
新聞は情報源として重要。1.5銭が175円だとすると
- 1銭の価値 = 175円 ÷ 1.5 = 約116円
- 三銭 = 116円 × 3 = 約348円
品目によってバラつきがありますが、物価ベースでは三銭が50円~350円の範囲に収まることが分かります。でも、現代のアンパン1個が100~200円だとすると、三銭=100円前後なら「安い」と感じるのは自然です。

でも、これだけでは当時の「高い!」の感覚が掴めません。物価はあくまで一側面。次に収入の視点に移ります。
2. 給与から見る三銭の重み
物価が安くても、収入が低ければ「三銭」は軽い出費にはなりません。昭和初期の労働者の給与を調べてみましょう。
- 工場労働者の日当:1円~2円
- 農作業者の日当:0.8円~1.5円
- 小学校教師の月収:約50円(公務員で比較的高め)
- 平均的な月収(20日労働):20円~40円
対して、2025年の日本では
- 最低賃金(全国平均):約1,200円/時
- 日当(8時間労働):約9,600円
- 月収(20日労働):約192,000円
- 正社員の平均月収:約300,000円(業種による)
日当ベースでの計算
昭和初期の平均日当を1.5円、現代を9,600円とすると:
- 1銭の価値 = 9,600円 ÷ 150銭 = 64円
- 三銭 = 64円 × 3 = 約192円
月収ベースでの計算
月収30円を192,000円に換算:
- 1銭の価値 = 192,000円 ÷ 3,000銭 = 64円
- 三銭 = 64円 × 3 = 約192円
給与ベースでは、三銭は現在の約190円に相当します。これは、収入に対する「三銭の割合」を現代に当てはめた結果です。
現代で日当9,600円の人が190円のアンパンを買うのは、約2%の出費。当時の日当1.5円で三銭も同じく2%。割合としては同じでも、生活必需品に使うお金が優先される時代では、この2%が「贅沢」に感じられた可能性があります。
3. アンパンの「三銭」が高い理由
ここで「アンパン」のシーンに戻ります。物価ベースで50円~170円、給与ベースで約190円。

現代の感覚だと「コンビニのパン並みなら安い」と思うのに、なぜドラマで「高い」と言われたのか?
経済的背景:貧富の差と購買力
昭和初期は関東大震災(1923年)の復興期から世界恐慌(1929年)へと向かう不安定な時代。都市部では工業化が進みつつも、農村部では貧困が深刻でした。労働者の日当1円~2円は平均値で、実際には1円未満の貧しい層も多かったのです。
米1kg(25銭)が日当の1/4を占める生活では、三銭(日当の2%)は「無駄遣い」に感じられたでしょう。一方、富裕層や都市の中産階級には三銭は軽い出費だったはず。
この貧富の差が、ドラマで「高い」と感じる庶民の声を際立たせているのかもしれません。
文化的背景:アンパンのポジション
アンパンは明治時代に木村屋が開発した「和洋折衷」の菓子パン。当初は高級品で、庶民に広まったのは大正~昭和にかけてです。昭和初期でも、和菓子(1銭)やおにぎり(1~2銭)に比べると「洋風」で「特別なおやつ」。
現代でも、伝統的な大福(50円)と洋風クロワッサン(200円)を比べると後者の方が高いですよね。アンパン三銭は、そば5銭や駄菓子1銭と比べると割高感があった可能性があります。
ドラマの視点:売り手と買い手のギャップ
「アンパン」で主人公が三銭で売ろうとしたのは、原価や労力を考えた「適正価格」のつもりだったのかも。でも、買い手である庶民には「日常食じゃないものに三銭は出せない」という心理が働いたのでしょう。
現代でも「100円で手作りパンなら安い」と売る側が思っても、消費者が「コンビニで80円なのに」と感じれば売れません。

このギャップが「高い!」の声につながったと想像できます。
4. 三銭から見える昭和初期の暮らし
三銭の価値を考えると、単なる金額以上のものが浮かび上がります。ここでは、関連するトピックを広げてみます。
三銭で何が買えた?
- 駄菓子:1銭で飴や煎餅が買えたので、三銭なら3個。子供のお小遣いの定番。
- 新聞:1部1.5銭なら2部読める。情報収集に使う大人の選択肢。
- 郵便:葉書が2銭、封書が4銭。三銭だと葉書1枚+お釣りで遠くの親戚に手紙を。
三銭は「小さな楽しみ」や「必要最低限の出費」に使われる額。現代の100円ショップやコンビニのプチ贅沢に似た感覚かもしれません。
三銭が映す社会
昭和初期は軍国主義への移行期でもありました。軍事費が増え、庶民の生活は圧迫されつつあった時代。三銭を節約して貯金する人もいれば、都市部ではカフェ文化が花開き、モダンガールが三銭でコーヒーを楽しんだかも。

同じ三銭でも、使う人の立場で価値が違ったんですね。
5. 現代との比較:三銭の感覚をどう捉える?
現代の150円~200円は、気軽に使える額ではありますが、毎日使うには少し考える金額です。
例えば
- コンビニの缶コーヒー:120円
- パン屋のアンパン:180円
- 電車賃(1駅):160円
昭和初期の三銭がこのくらいだとすると、「特別な日に食べるおやつ」や「ちょっとした移動」に使う感覚に近いですね。現代では収入も物価も高い分、三銭の「重み」は薄れているとも言えます。
当時の庶民にとって、三銭は「選択を迫られる金額」だった。それが「アンパン」で「高い」と言われた理由の一端でしょう。
Q&A
-
三銭で他に何が買えた?
-
三銭なら、駄菓子3個(1銭/個)、新聞2部(1.5銭/部)、または葉書1枚(2銭)+お釣りで手紙が出せました。庶民には「小さな贅沢」や「必要経費」に使う額で、現代の100円ショップでの買い物に似た感覚です。
-
アンパンが三銭って本当に高かった?
-
当時の感覚では「やや高い」です。そば5銭やおにぎり1~2銭に比べ、アンパンは「洋風」で特別なおやつ。三銭は日当1.5円の2%で、現代で日当1万円の人が200円のパンを買うくらいの負担感があったと考えられます。
-
昭和初期の物価はどれくらい?
-
米1kgが25銭、そばが7銭と、現代の1/1000程度の価格帯。ただし、収入も低く、日当1円~2円が普通。物価と収入のバランスで見ると、生活必需品以外への出費は慎重だった時代です。
-
ドラマ「アンパン」の時代背景って?
-
昭和初期は関東大震災後の復興期から世界恐慌へ向かう転換期。都市では洋風文化が広がりつつも、農村や貧困層は厳しい生活を強いられていました。アンパンが「高い」と言われるのは、そんな庶民の現実を反映しているのでしょう。
-
三銭の価値はどうやって計算した?
-
物価比較(米やそばの価格)と給与比較(日当や月収の割合)の2つの方法を使いました。物価では50円~170円、給与では約190円と算出し、生活感覚を加味して150円~200円と結論付けています。
まとめ:昭和初期の三銭は現在のいくらか
昭和初期の三銭を現在の価値に換算すると
- 物価ベース:50円~170円(品目による)
- 給与ベース:約190円
- 生活感覚ベース:150円~200円
現代の私には「アンパン150円なら安い!」と感じますが、当時の庶民には「日々の生活の中で優先度が低いものに三銭は惜しい」という感覚があったはず。

ドラマ「アンパン」の「高い!」は、単なる価格の問題ではなく、貧しさの中での選択や、洋風文化への戸惑いを映しているのかもしれませんね。
三銭という小さな金額から、昭和初期の経済、暮らし、価値観が垣間見えるのは面白いですよね。ドラマを見ながら「当時の人々はこんな風に暮らしていたんだ」と想像すると、歴史が身近に感じられます。
あなたはどう思いますか?三銭から広がるストーリーに、どんな思いを馳せますか?
覚えておきたいポイント
- 三銭は現代で150~200円
- 物価ベースでは50~170円
- 給与ベースでは約190円
- アンパンは当時「特別なおやつ」
- 三銭は日当の2%で負担感あり
- 昭和初期は貧富の差が大きかった
- 米1kgが25銭、そばが7銭
- アンパンが「高い」は庶民の声
- 洋風文化はまだ馴染み薄かった
- 三銭から歴史と暮らしが見える



