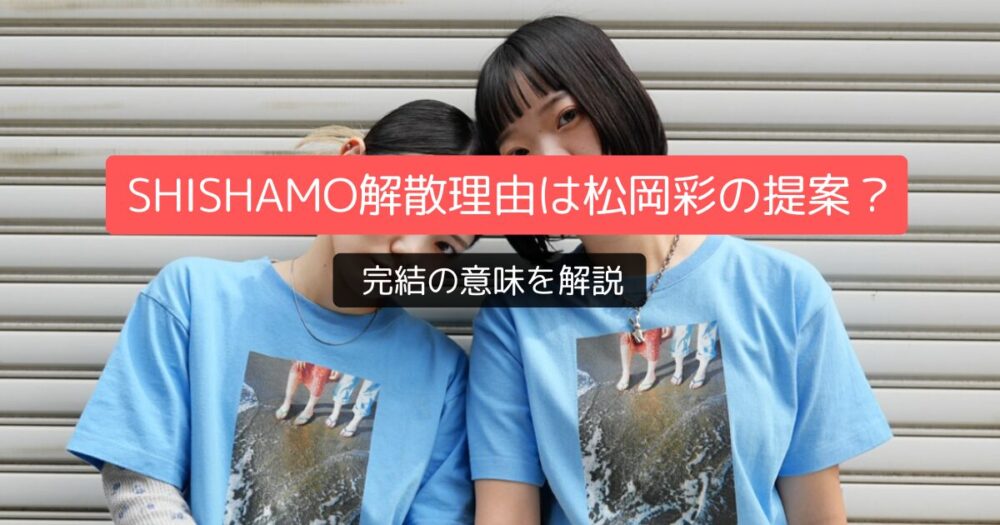今回は、朝ドラ「ブギウギ」で話題の作曲家・黎錦光((れいきんこう)と、その役を演じた日本人俳優・浩歌…
【ばけばけ 小泉八雲の左目】が変なのはなぜ?トミー・バストウが特殊メイクで再現した「白い星」、失明原因と隻眼作家が掴んだ怪談文学の核心
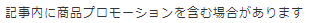
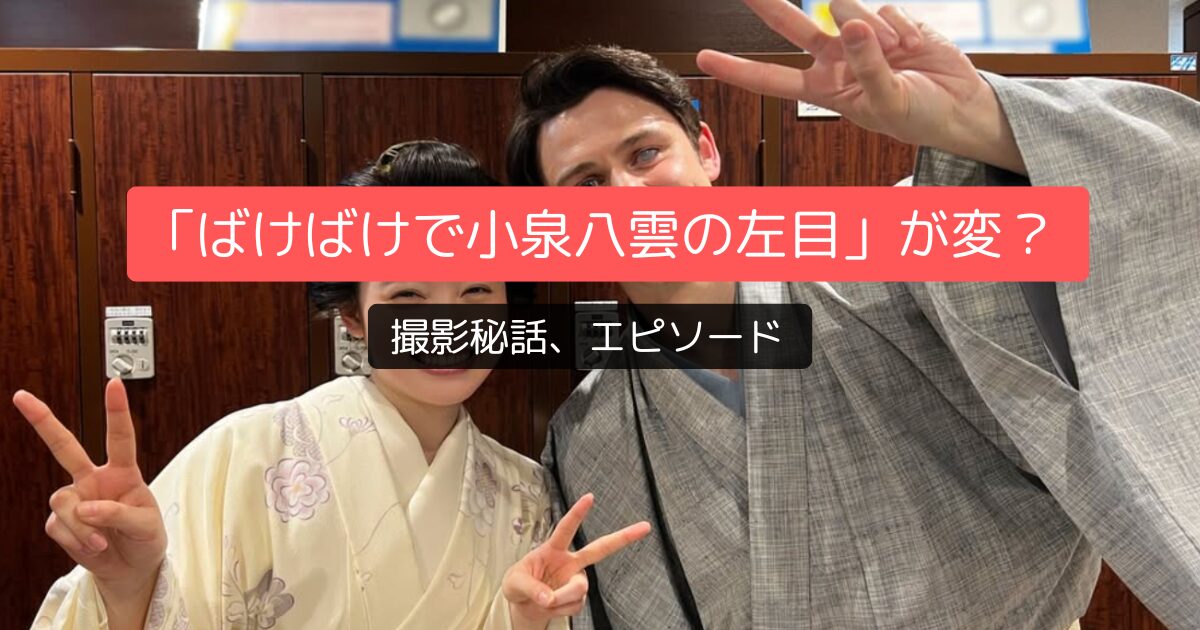
結論:朝ドラ『ばけばけ』のヘブンの左目が白濁しているのは、モデル・小泉八雲が16歳で失明した痕跡を忠実に再現したもの。この視覚障害が、後に世界的な怪談作家を生み出した。
2025年9月29日(月)に始まったNHK朝ドラ『ばけばけ』で、トミー・バストウ演じるレフカダ・ヘブンの左目の色がおかしいと思ったかたも多いはず。
視聴者が疑問に思う「白い星」のような濁りは、実はヘブンのモデル・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が背負った悲劇的過去の忠実な再現なのです。

今回はこの「変な色」の理由と、失明が生んだ文学的才能の秘密に迫ります。
この記事でわかること
・八雲の左目失明は16歳のロープ事故が原因
・生涯義眼を拒み「白い星」を晒し続けた理由
・視覚障害が怪談文学の才能を開花させた経緯
・トミー・バストウの特殊メイクによる忠実再現
・失明体験がクレオール文化愛に与えた影響
・『ばけばけ』をより深く楽しむ視点
【ばけばけ 小泉八雲の左目】なぜトミー・バストウの特殊メイクが話題?16歳の悲劇が生んだ「白い星」の真実と怪談文学への影響を徹底解説
1866年の事故:「Giants Stride」という遊戯が奪った視力
八雲の左目失明は1866年、彼が16歳の時に起きました。場所はイギリス・ダーラムのカトリック系寄宿学校「アショー・カレッジ」。
左目の失明は、1866年、16才のときに在学していたカトリック系の学校である「アショー・カレッジ(セント・カスバート・カレッジ)」において、"The Giants Stride"という遊びをしているときに友人が放った縄の先が、左目に当たったことによるものです。
「Giants Stride(巨人の歩幅)」は19世紀のイギリスで人気だった遊戯でした。高い柱から伸びた複数の縄を子どもたちが握り、円を描くように走り回る遊びです。

その縄の結び目が、不運にも八雲の左眼球を直撃したのです。
この事故により八雲は長期療養を余儀なくされました。傷は化膿し、生来ひどい近視だったが在学中遊戯をして左眼を傷つけ失明した状態となります。
治癒後、左目には白く濁った膜状の組織が残り、英文学者・田部隆次は「左の眼球の上に白い星がかかった人」と表現したのです。
ばけばけで小泉八雲役のトミー・バストウさんの左目が少しおかしいなと思ったら、小泉八雲は16歳の時に失明したからその役柄上の演出でトミー・バストウさん自身に障害があるわけではないことを今知りました🙏🏻#トミー・バストウ #小泉八雲 #ばけばけ #朝ドラ #NHK
— 宮内信之 (@Nobuyu_Miyauchi) September 28, 2025
義眼を拒み続けた八雲の美学:「偽りで傷を隠さない」誇り
八雲は生涯を通じて義眼や眼帯の使用を拒みました。息子・小泉一雄氏の証言によると、父は「偽りで傷を隠すことを潔しとしなかった」そうです。
これは恥ずかしさを隠すためではなく、むしろ自らの不完全さを受け入れる美意識の表れでした。
私が興味深いと感じるのは、この選択が八雲の文学的立ち位置と完全に重なることです。
彼は西洋化する日本に対し「そのままの日本こそ美しい」と主張しました。自分の傷を隠さない姿勢は、まさに「ありのまま」を肯定する哲学の体現だったのでしょう。
トミー・バストウの特殊メイク:6~7回の試作を重ねた渾身の再現
朝ドラ制作陣は、この史実を極めて忠実に再現しました。トミー・バストウさんの左目には、特別なコンタクトレンズによる特殊メイクが施されています。
制作統括の橋爪國臣氏によると、実は設定上「失明していない」選択肢もありました。しかしトミーさん自身が「本格的に取り組みたい」と希望し、八雲と同じ失明設定での出演を強く要望したのです。
特殊レンズは6~7回の試作を重ね開発されました。当初は「左目がほとんど見えない状態」で、装着に30分以上かかっていました(現在は演技に支障のない改良版を使用しています)。

これはトミーさんの役への真摯な取り組みが伺えるエピソードです。
二重の視覚障害:右目も強度近視という過酷な現実
八雲の苦労は左目の失明だけではありませんでした。生来ひどい近視だった右目も強度の近視で、読書や執筆には極度の眼精疲労が伴いました。
この制約は、現在残る八雲の執筆机からも明らかです。この机 けっこう高さがあるんです。現代の机と比べても高い。
立ったまま字が書けるぐらいに高いんですと、八雲旧居を訪れた人は証言しています。身長160cmと小柄だった八雲が、顔を机に近づけて執筆する必要があったからなんですね。
聴覚世界への没入:音が育んだ文学的感性
視覚の制約は、八雲の他の感覚を研ぎ澄ませました。彼の作品は、音・匂い・空気の湿り気といった非視覚的要素に満ちています。

私はこの「不便さ」こそが八雲文学の真髄だと考えています。
現代のAI音声入力があれば、彼の肉体的苦労は激減したでしょう。しかし、その代わりに妻セツの語りや、下駄の音、虫の声といった音の世界への集中力も失われていたはずです。八雲にとって不自由は、芸術の深度と直結していました。
『怪談』と隻眼の符号:「耳なし芳一」が暗示する八雲の心境
八雲の代表作『怪談』の冒頭「耳なし芳一」の主人公は、盲目の琵琶法師です。視覚を失った芳一が、聴覚を頼りに平家の怨霊という「見えない存在」と交流する物語構造は、八雲自身の体験と重なります。
八雲は、身体的な欠損を独自の創作力の源泉として昇華させました。芳一の物語は、八雲が隻眼という試練を乗り越え、作家として再生した軌跡の寓話なのです。
※:隻眼(そうがん):片方の目が見えない状態
19歳の単身渡米:失明と破産が重なった人生の分岐点
八雲の人生に追い打ちをかけたのが、17歳時の経済的破綻でした。彼を養育していた大叔母が投機に失敗し破産。失明という個人的不幸と、経済基盤の崩壊という二重の困難が重なったのです。
結果、八雲は19歳で単身アメリカへ渡ることになります。この時点で、彼の流浪人生が始まりました。隻眼のハンディを背負いながら、異国で生計を立てる過酷な日々の始まりです。
クレオール文化への共感:混血児としてのアイデンティティ
アイルランド系の父とギリシャ系の母を持つ八雲は、自らを「混血児」と位置づけていました。この経験から、主流文化から外れた存在や、異文化が混ざり合うクレオール文化に深い共感を抱きます。
アメリカ時代の八雲は、ニューオーリンズのクレオール料理に魅了され、1885年には料理本『ラ・クイジーヌ・クレオール』まで出版しています。
彼は当時同棲していたアフロアメリカン(黒人女性)と結婚したくて、それが許される州、ニューオーリンズに引っ越したという記録もあり、彼の文化的境界線への関心が窺えます。
日本での「骨を埋める」決意:46歳の帰化という選択
40歳で来日した八雲は、松江で教師として安定した職を得ます。そしてセツ(トキのモデル)との結婚により、初めて精神的な安寧を見出しました。
1896年に日本へ帰化し「小泉八雲」と名乗ったのは、形式的手続きではありません。日本に「骨を埋める」という強い意志の表れでした。

興味深いのは、八雲が妻セツの語る出雲方言を愛し、翻訳時に意図的に日本語を残したことです。
彼は日本語を、自分が愛してきたクレオール言語として捉えていました。八雲にとって日本語は、西洋化の波に飲まれる前の、混淆文化の宝物だったのです。
統計に現れない少数者の視点:視覚障害者として生きた明治時代
19世紀後半の明治初期は、視覚障害者への社会的サポートや医学的治療が未発達でした。八雲の失明体験は、まさに「統計外」の少数者としての生き方を強いられた証拠です。
この体験が、八雇の文学に普遍的な孤独感と居場所探しのテーマを与えました。現代を生きる私たちにも通じる、根源的な人間の悲しみと希望の物語として響くのです。
『ばけばけ』が描く「隻眼の視線」:愛のまなざしの象徴
朝ドラ『ばけばけ』でのヘブンの「隻眼の視線」は、身体的障害の再現だけではありません。喪失を乗り越え、人間の心の奥深さに触れようとした作家の、静かで深い愛のまなざしを象徴しています。
八雲の「白い星」は彼の文学的羅針盤でした。異界と現実、西洋と日本、そして傷と再生の境界線を見つめる指標だったのです。

現代の私たちも、この視点から学べることは多いはずです。
まとめ:『ばけばけ』小泉八雲の左目が変なのはなぜ?
朝ドラ『ばけばけ』でトミー・バストウさんが再現した小泉八雲の「左目の白い星」は、16歳のロープ事故で生じた失明の痕跡でした。この身体的制約は、八雲の感性を研ぎ澄まし、世界的な怪談作家を生み出す源泉となったのです。
八雲が義眼を拒み、傷を隠さなかった姿勢は、不完全さを肯定する美学の体現でした。その思想は、日本文化への愛情と深く結びついています。
『ばけばけ』視聴時は、ヘブンの左目に注目してください。それは恐怖の演出ではなく、愛と理解の象徴です。私たちは八雲の「白い星」を通して、目に見えるものだけが全てではないと気付かされるでしょう。
でもねぇ、ヘビとカエルは必要だったのかな?これもなにかの伏線かもしれませんね。
覚えておきたいポイント
・八雲の失明は16歳の「Giants Stride」遊戯事故
・左目に残った白濁を「白い星」と表現
・生涯義眼や眼帯の使用を拒否し続けた
・右目も強度近視の二重視覚障害
・視覚制約が聴覚・想像力を研ぎ澄ませた
・『怪談』の「耳なし芳一」は自身の投影
・混血児として流浪の人生を送る
・40歳で来日、46歳で日本に帰化
・妻セツの出雲方言をクレオール愛で受容
・トミー・バストウが特殊メイクで忠実再現