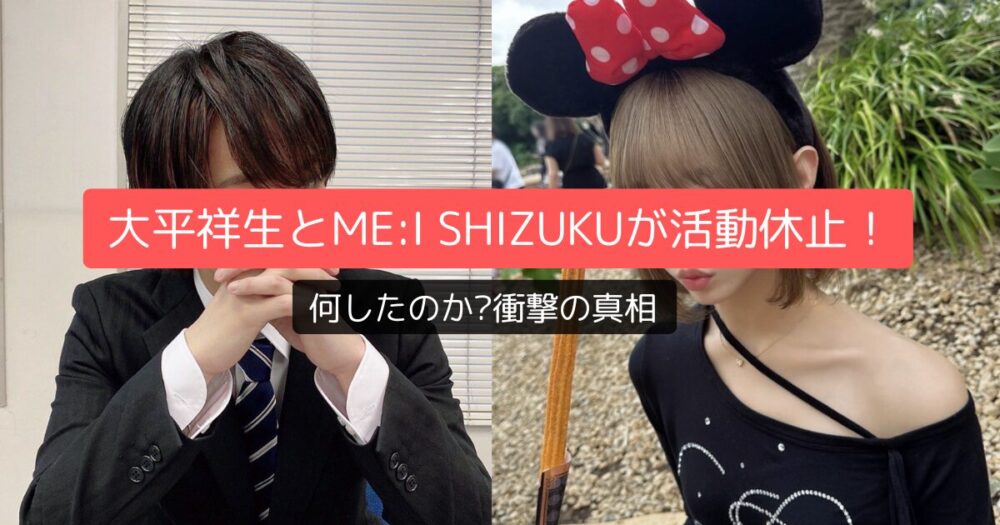日本の伝統芸能、落語の世界に新たな動きがありました。 長い歴史を持つ人気番組『笑点』の大喜利メンバー…
朝ドラ「ばけばけ」ヘビとカエルが登場する理由を徹底考察
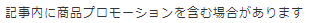

朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の第1回冒頭、CGIで描かれたヘビとカエルが登場し、視聴者に大きなインパクトを与えました。しかも、その声を担当するのが人気お笑いコンビの阿佐ヶ谷姉妹(渡辺江里子さん、木村美穂さん)という斬新な設定です。
ヘビやカエルといった生き物に対して、正直「気持ち悪い」と感じた方もいるでしょう。実は、私も「なぜ朝ドラの顔として、あえてこの組み合わせを?」と疑問に感じた一人です。
でも、このユニークな「蛇と蛙」の登場には、ヒロインのモデルとなった人物、そしてドラマの根幹をなすテーマに深く関わる、非常に重要な理由が隠されていました。

本記事では、制作統括のコメントに基づいた「蛇と蛙」起用の公式な理由から、生物学や日本の伝承における彼らの意味合いまでを深掘りし、「ばけばけ」がこの2匹を通じて何を伝えたいのかを徹底的に考察します。
【ばけばけ】ヘビとカエル起用の理由―小泉八雲の逸話と逆転の美学
月曜からの朝ドラ『ばけばけ』
— セレニティ (@Lemonpanna7) September 26, 2025
主人公夫妻を見守る "蛇と蛙の阿佐ヶ谷姉妹" で俄然楽しみになってしまった✨ pic.twitter.com/ds6f0qY8hN
制作陣が明かした公式理由―小泉八雲の「情け」エピソード
朝ドラ「ばけばけ」初回冒頭。CGで描かれたヘビとカエルが登場しましたが、調べると、この2匹には深い意味がありました。
主人公・松野トキ(高石あかり)のモデルは小泉セツ、夫ヘブン(トミー・バストウ)のモデルは小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)です。
制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーによれば、八雲の家にはヘビとカエルが実際に住んでいたといいます。
『ばけばけ』阿佐ヶ谷姉妹のヘビとカエルには意表をつかれて笑いました。写真はむかーし小泉八雲記念館で買った小物入れ。カエルが好きだったへるん先生が愛用していた廃ペン皿を模したものだそう。蓮に乗ったカエル君が可愛いんです#ばけばけ https://t.co/CcZiHAS74a pic.twitter.com/jXYUuv2qNI
— アトリエmao@10/30新潟コミティア委託予定 (@ateliermao) September 29, 2025
さらに驚くべきは八雲が残した文章です。
「池のカエルをヘビが食べようとしていて、かわいそうだから自分の食事をヘビの前に置いた。その間にカエルが逃げられるようにした」。
捕食者と被食者、本来なら殺し合う関係を、八雲は自分の食事で仲裁したわけです。しかも八雲の自画像はカエルだったとか。
脚本家ふじきみつ彦氏はこの逸話をもとに、ヘビとカエルを語り役として提案しました。橋爪氏は「物語を語るのではなく、トキとヘブンをそっと見守る存在にしたかった」と説明します。

だからクレジットでは「ナレーション」ではなく「登場人物」扱いです。物語の外ではなく、中にいる。そこが肝なんですね。
なぜ気持ち悪さを押してまでヘビとカエルなのか―異形が問う逆転の美学
制作陣も分かっていたはずです。CGのヘビとカエルを見て「気持ち悪い」と感じる視聴者がいることを。それでも初回冒頭に出してきた。なぜか。
私はここに「ばけばけ」の核心を見ます。見た目で判断するな、という挑戦状です。
筆者の考察1:逆転の象徴としての異形
「ばけばけ」の舞台は西洋化が進む明治日本。怪談を愛する夫婦の物語です。怪談は見た目が怖ろしくても、裏には人の「情」が潜んでいます。
第1回では主人公の父が、勤勉な優秀父でもダメ父でもなく「立ち尽くしちょる」父として描かれました。従来の朝ドラ父像をひっくり返しています。
ヘブンはトキが「学がない」と恥じる態度を「おばけの話はすばらしい」と逆評価しました。
ヘビとカエルも同じです。捕食者と被食者、本来なら敵対する2匹を、親しみやすい阿佐ヶ谷姉妹の声で「仲良し」として出す。視聴者に「生理的嫌悪を超えて本質(温かい見守り役)を受け入れてほしい」と訴えているんですね。

この不快感を乗り越える体験こそ、「ばけばけ」が描く逆転の美学ではないでしょうか。
「ヘビににらまれたカエル」は古い?生物学が明かす新解釈
ヘビとカエルといえば「ヘビににらまれたカエル」という諺が有名です。恐怖で体がすくむ様子を指します。
ところが近年、この解釈が根底から覆りました。
恐怖ではなく「戦略的我慢比べ」
京都大学の西海望研究員(当時)と森哲准教授の研究チームが2020年に発表した研究で、カエルとヘビが対峙して動かない現象は恐怖ではなく双方の戦略的判断だと明らかにしました。
先に動くと相手の対抗手段に弱くなる。だから両者とも「後手に回ろう」とする。結果、我慢比べのような硬直状態が生まれるわけです。
研究者は「この諺は恐怖の例えではなく、危機を切り抜けようと虎視眈々と狙う状況の喩えとして使う方が生物学的に正しい」と指摘しています。
この新解釈は「ばけばけ」の世界観と重なります。カエルはただの弱者ではありません。大型のカエルはヘビを捕食することもあります。

明治の激動期、没落士族の娘トキがただ時代に流されるのではなく、静かに強く生きる「賢い弱者」をカエルが象徴している。そう読むと面白いですよね。
日本の伝承に刻まれたヘビとカエルの特殊な絆
ヘビとカエルは八雲のエピソードだけでなく、古くから日本の民話や信仰で特別な関係を持ってきました。
捕食を超えた恩返し譚
日本の民話には「蛇が蛙を呑もうとするのを人が助け、蛙がその恩返しに人を救う」という恩返し譚が多数あります。
たとえば「まんが日本昔ばなし」にも収録された大分県の昔話「蛇と蛙」。神様が動物の食べ物を決める際、怠惰だったカエルがヘビを馬鹿にしたため、ヘビはカエルを食べるよう定められた、という話です。
ヘビはカエルにからかわれた仕返しに、尻から飲み込むようになったとされます。
またヘビは古来、水神や田の神、屋敷神として信仰されてきました。水の守護者として、水の象徴カエルと密接な関係にあります。同時に「贄」としてカエルを食べる関係でもある。複雑ですよね。
筆者の考察2:八雲夫妻の庭が示す「情」の共存空間
八雲がヘビとカエルに自分の食事を与えたエピソード。これは本来敵対する二者が、人為的な「情」で一時的に共存した稀有な状態を示しています。
「ばけばけ」の庭で、阿佐ヶ谷姉妹の声で仲良く(あるいは軽口を叩き合いながら)夫婦を見守るヘビとカエル。これは八雲夫妻が築いた、異文化・異形・異なる価値観を包み込む調和的な家庭環境のメタファーではないでしょうか。

愛と理解があれば、本来相容れないものも共存できる。そんな希望の象徴だと私は考えます。
阿佐ヶ谷姉妹起用の狙い―ユーモアという緩衝材
CGヘビとカエルに阿佐ヶ谷姉妹を起用した点も重要です。
【決定】阿佐ヶ谷姉妹、次期朝ドラ『ばけばけ』に蛇と蛙役で朝ドラ初出演https://t.co/MFkKNslje3
— ライブドアニュース (@livedoornews) August 27, 2025
ヒロイン・松野トキと小泉八雲がモデルとなったヘブンの家の庭に住む「蛇」と「蛙」の声を務める。二人の歩みを優しく見守る。阿佐ヶ谷姉妹は「大役にビックリした」「うれしかったです」と喜んだ。 pic.twitter.com/IOZQXVXFbH
脚本家との信頼と視聴者への寄り添い
脚本家ふじきみつ彦氏は以前NHKよるドラ「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」を執筆しており、2人をよく知る間柄です。
橋爪氏は起用理由を「ドラマを楽しく観られるし、視聴者も一緒に寄り添ってくれると思った」と語ります。2人の漫才の立ち位置から、自然とヘビ(渡辺江里子)とカエル(木村美穂)の担当が決まったとか。
ふじき氏はNHKドラマ・ガイドで「つらいシーンでもお2人の声が穏やかで笑える空気を作ってくれたら」と語っていたとか。彼女たちの声に物語の重さを和らげる「スパイス」役を期待しているわけですね。
筆者の考察3:辛い時代を生き抜くための心の余白
明治時代、没落士族として生きたトキの人生には辛い出来事が多く起こることが示唆されています。
この重い時代背景と個人の苦悩を描くとき、CGヘビ・カエル、そして阿佐ヶ谷姉妹の穏やかでユーモラスな声は、視聴者が感情移入しすぎないための「緩衝材」として機能します。
2匹が「朝よ、夜だけど」「朝だけど、夜よー」と朝と夜の違いで慌てるシーン。これは新しい時代で価値観がひっくり返る(逆転する)現象を、深刻になりすぎず表現する絶妙なコメディタッチです。
この「気持ち悪い」と「可愛らしい」の境界線で漂うヘビとカエルの存在こそ、「ばけばけ」が目指す、辛い現実をユーモアで乗り越える視点そのもの。私はそう確信しています。
まとめ:【ばけばけ】ヘビとカエル起用の理由
朝ドラ「ばけばけ」初回のヘビとカエルは、奇抜な演出ではありませんでした。
3つの理由で起用されています。
- 実在モデルとの繋がり: 小泉八雲とセツが愛した庭の生き物。八雲が捕食関係に「情け」をかけたエピソードに基づきます。
- 物語内の役割: 「登場人物の一人」として、ヒロイン夫妻の人生を滑稽に、温かく見守る存在です。
- テーマの体現: 見た目や常識が逆転していく明治時代で、異形や相反するものの共存、弱者の戦略的賢さを象徴しています。
最初は見た目に驚いても、このヘビとカエルが時代の激流で必死に生きるトキとヘブンを応援し、見守る存在だと分かれば、きっと愛着が湧いてきます。阿佐ヶ谷姉妹の優しい声と共に、2匹の「我慢比べ」のような長寿の歴史を、温かく見守っていきましょう。