芸能界の裏側には、思わず目を見張るような驚きの噂やエピソードがたくさん隠れているようです。 中でも特…
映画「近畿地方のある場所について」の舞台はどこ?もっとも有力な場所は、大阪府河内長野市に実在する滝畑ダムか
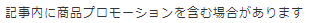
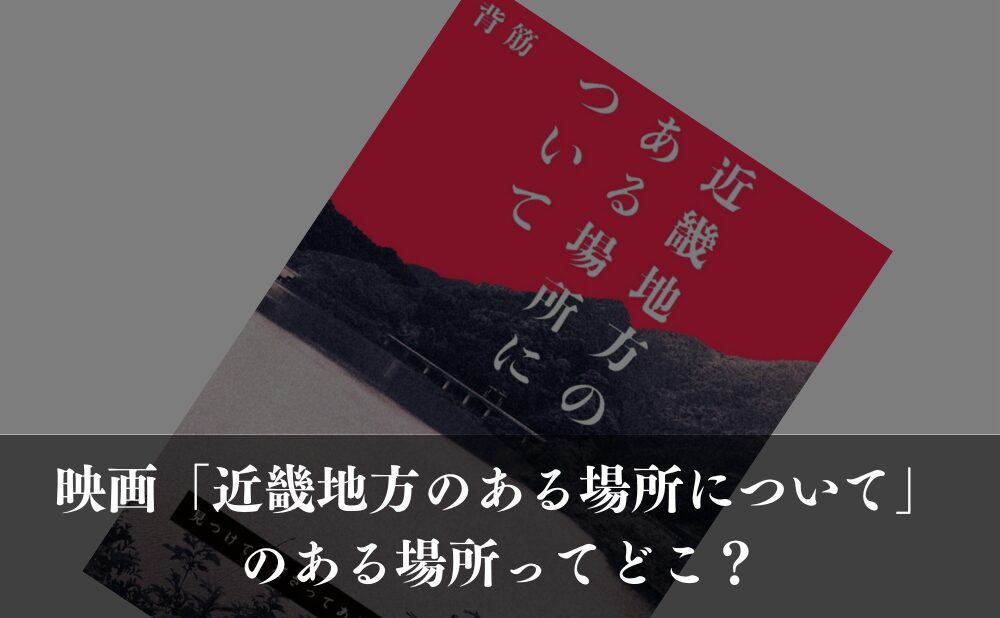
公式には明言されていないものの、原作小説の表紙に描かれた階段や祠が、滝畑ダム周辺の実際の風景と驚くほど一致しているのです。まさに鳥肌が立つほどの一致度。
ホラー小説「近畿地方のある場所について」が2025年8月8日に実写映画化され、公開前から多くのファンや考察勢の間で「あの"場所"はどこなのか?」という疑問がやはり多いですね。
この作品がこれほど話題になる理由は、その巧妙な仕掛けにあります。
原作がSNSの書き込みや雑誌記事、インタビューを駆使したモキュメンタリー形式で作られており、現実と錯覚させるほどのリアリティがあるため、読者や観客は自然と「これは本当にあったことなのでは?」と深く作品世界に引き込まれてしまうのです。

今回は、映画「近畿地方のある場所について」の舞台はどこ?について深堀りと考察をしていきます。
この記事でわかること
- ホラー舞台は実在地がモデル
- 恐怖は曖昧描写と読者参加で増す
- 大阪魅力は人情と多様グルメ
- 都市伝説は歴史と文化を反映
- 地元好みのスポットが人気
- 観光プロはグルメと人情を提案
映画「近畿地方のある場所について」の核心!それは一体どこなのか?
近畿地方ほか全国劇場で大ヒット上映中⛰️
— 映画『近畿地方のある場所について』公式アカウント (@kinki_movie) August 8, 2025
⠀
『#近畿地方のある場所について』
感想投稿キャンペーンを開催します。#情報をお持ちの方はご連絡ください
で投稿してください。
キャストサイン入りポスターや登山グッズ等
39名にお礼もあります。サンキューです。
ときどき申し上げる場合もあります。
映画「近畿地方のある場所について」の舞台とされる「ある場所」は、公式には具体的に明かされていません。
しかし、多くのファンや考察勢の間では、大阪府河内長野市に位置する滝畑ダムがそのモデルである可能性が極めて高いと結論づけられています。
公式は語らずとも、ファンが辿り着いた「ほぼ確定の場所」
『近畿地方のある場所について』のロケ地について、ファンが滝畑ダムであると確信しているのには、いくつかの具体的な理由があります。

原作小説の表紙に描かれている象徴的な階段や祠が、実際に滝畑ダム周辺に存在する実景と驚くほど酷似している点が最大の根拠です。
「近畿地方のある場所について」の表紙が滝畑ダムっぽいんよなー。
— O-chang≒シントサカフレッシュ (@Ochang_toxic) March 18, 2024
かのダムは数十年前から怪談スポット的に扱われてるし。実際現場に行くとのどかな感じやねんけど一回だけ付近の道路を走ってたらえらい狭くて何これ?な道路に迷い込んだ事がある。 pic.twitter.com/1zygCuKmJh
兵庫県の一庫ダムも候補として挙がっています。一庫ダムの規模や景観が作品の雰囲気と重なる可能性、兵庫県全体が近畿地方の舞台として自然な選択肢であることも理由の一つです。
実際に、兵庫県は多くの映画やドラマのロケ地となっており、「神戸市」や「西宮市」などが舞台の作品が数多く存在します。
映画『近畿地方のある場所について』
— ヴィヨンド (@hankyukurasuta) August 8, 2025
再度グーグルアースで出そうとしても、位置共有を拒否されて出せないから魚拓した。
一庫ダム
妙見山 pic.twitter.com/kCr1Wu5zIr
その他、滋賀県も映画「ぶぶ漬けどうどす」のロケ地になっていますし、和歌山県には「サマータイムレンダ」の聖地として知られる友ヶ島があります。このように関西各地には、コンテンツの舞台となった場所が点在しているのです。
では、なぜ公式は「ある場所」の具体的な地名を明言しないのでしょうか?その意図としては、以下の3点が考えられます。
実在地域への配慮:原作が怪異や失踪事件といったセンシティブなテーマを扱っているため、実際の地名を明かすことで地元に風評被害が及ぶことを避けている可能性が高いです。特に日本では、心霊スポットとして有名になることで、夜間の騒音や不法侵入といった問題が起こりがちです。
モキュメンタリーとしての演出:物語の特性上、「実在しそうで実在しない」という曖昧さが恐怖の一部となっています。観客や読者の想像力を刺激し、フィクションを事実と錯覚させる演出効果を狙っているのでしょう。私もこの「もしかしたら現実かも」という感覚にまんまとハマってしまいました。
ファンの考察文化の促進:作品の人気を高めるため、SNS上で「ここでは?」「この看板がヒントかも」といった自主的な考察が生まれるよう、あえて情報を伏せる戦略も見られます。この「謎解き」要素こそが、読者を作品に深く引き込むフックになっていると感じます。
この「場所を隠す」という手法こそが、現代のホラー作品において最も効果的な「恐怖の演出」なのかもしれません。
見る側、読む側の想像力を最大限に掻き立て、あたかも自分がその「謎」を解き明かしているかのような錯覚に陥らせる。これはフィクションを超えた体験であり、作品が持つメッセージ性をより深く心に刻むことにも繋がっていると思います。
原作と映画が紡ぐ「近畿地方のある場所」の深い闇
「近畿地方のある場所について」の原作小説は、Web小説サイト「カクヨム」で2023年1月に連載が開始され、累計2300万PVを超える大ヒットを記録しました。これは相当な数字で、Web小説の中でもトップクラスの人気を誇っています。
この作品は、モキュメンタリー形式で展開され、「山へ誘うモノ」「ジャンプ女」「了あきら」という三種類の怪異が物語の核心を成しています。
これら怪異は、SNSやネット掲示板の書き込み、インタビューテープの文字起こし、古い雑誌記事といった断片的な情報を通じて語られ、読者はまるで自分で調査しているかのような没入感を味わえます。
映画版は、2025年8月8日に全国公開され、白石晃士監督がメガホンを取り、菅野美穂と赤楚衛二が主演を務めています。
白石監督は、自身のホラー作品『ノロイ』に共通項を感じたことから、本作の映画化に強い意欲を示しました。

監督自身、連載当初から原作を読んでいたというから、まさに運命的な出会いですね。
原作から映画への再構築において、製作陣は原作者の背筋氏と密に連携。小説の叙述トリックを映像で再現する難しさから、映画では主人公の記憶やトラウマに焦点を当てるなど、映像ならではのオリジナル展開が加えられています。
菅野美穂さんと赤楚衛二さんの演技は、文字では伝えきれない「空気」や「違和感」をリアルに表現し、観客を作品世界に引き込んでいきます。普段のイメージとは異なる彼らの「変化」は、本作の大きな見どころだとプロデューサーも語っています。
この作品が持つ「読むことで呪いが始まる」「観たらゾワッとする」という構造的恐怖は、怖い話だけにとどまりません。情報・記憶・呪いの連鎖を現代社会と照らし合わせて考察できる深みを持っているのです。
SNSやスマホが普及した現代において、インターネットはすでに恐怖の「土台」となっていると白石監督は述べています。
作中で幽霊が「ネット民的な動き」をする描写は、まさに現代的な「気持ち悪さ」を表現。
映画の撮影現場では、まるで作品の怪異が現実世界に現れたかのような怪奇現象が続出したという裏話があります。
㊗️公開記念㊗️
— ASUKA NEMOTO|映画録音 (@nemoasu) August 8, 2025
『近畿地方のある場所について』の撮影現場で起きた最恐怪異VS白石監督
トンネル内で誰も触れていないのに揺れ続ける袋に近づいた監督は…#近畿地方のある場所について#菅野美穂#赤楚衛二#白石晃士#ホラー pic.twitter.com/J2WrcuCNqg
赤楚衛二さんのお祓い中の神主の異変、菅野美穂さんが清めの塩を持ち歩いていたこと。撮影映像が原因不明で真っ黒になったり、心霊スポットのトンネルで謎の人影や声が確認され、体調不良を訴えるスタッフもいたそうです。
プロデューサーの櫛山氏自身も、ロケハン中に車のタイヤがパンクしたり、見知らぬ老婆から謎の電話がかかってくるという体験をしています。
これは「マジ!?」ですよね。このエピソードは、作品の持つ「呪い」のテーマをより一層際立たせています。
この作品はホラー映画としてだけではなく、現代社会における情報過多と心理的な脆弱性を巧みに突いています。
インターネットを通じて拡散される「情報」が、ときに「呪い」のように個人の意識を蝕む様は、私たち自身の日常にも潜む恐怖を想起させます。
物理的な場所の恐怖だけでなく、情報空間という「見えない場所」に潜む恐怖を描いている点が、この作品の真の怖さだと感じます。
映画化でさらに増幅する「リアルさ」と「謎解き」の魅力
映画『近畿地方のある場所について』は、小説の映像化だけではなく、そのモキュメンタリースタイルと謎解き要素を最大限に引き出すことで、観客にこれまでにない没入感を提供しています。
一般社団法人日本映画製作者連盟(映連)によると、毎年1月に前年の映画産業に関するデータが発表されています。
2025年の映画興行収入において、日本のアニメ映画は国内外でますます注目を集めており、2024年に公開された『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』は、国内興行収入で158億円を記録しています。こうした市場環境の中で、本作は独特な作風で差別化を図っています。

映画は、行方不明になったオカルト雑誌の編集者が調べていた未解決事件や怪現象を、同僚の編集部員・小沢(赤楚衛二)とオカルトライターの千紘(菅野美穂)が追う物語です。
彼らが集める情報は、幼女失踪、中学生の集団ヒステリー、心霊スポットでの動画配信騒動など、過去の様々な出来事につながり、やがて「近畿地方のある場所」に収束していきます。
この情報の断片が繋がっていく過程が、観客にとってはまさに「謎解き体験」です。
原作が持つ「読むことで呪いが始まる」という構造的恐怖は、映画版では映像と音響によってさらに強化されています。白石監督は、1フレーム単位で「切る?伸ばす?」と悩むほど、テンポとリズムを重視したと語っています。
監督は「1秒たりとも観客を退屈させたくない」という思いで、103分の映画を無駄なく構成したそうです。
映画では、オリジナルの展開や昔話のシーンも盛り込まれており、これも原作者の背筋氏がアイデアを提供し、白石監督が素晴らしい形で昇華させました。
特に「お化け」を「人間っぽい」と表現する背筋氏の視点と、白石監督の「暴力のメタファーとしての霊」という視点が融合することで、単なる幽霊ではない、より根源的な恐怖が描かれています。
これは、私たち人間が持つ内面の闇や、社会の不条理さが形になったものとも言えるでしょう。
ただ、一部の映画レビューでは、期待値が高すぎたために「ホラー的な驚きが皆無だった」「謎解きが中途半端」といった厳しい意見も見られます。
ジャンプスケア(急な音で驚かせる演出)に頼りすぎている点や、主人公がすでに「ほぼ完成している答え」を追うだけで、自ら謎を解き明かす能動性が低いという批判もあります。
それでも、この映画は、現代のテクノロジーと融合した新しいホラーの形を提示しています。
例えば、大阪駅では、駅ビル全体を舞台にした大規模な謎解きイベントが開催されており、参加者は施設内を歩き回りながら謎を解き、クーポンや豪華景品を獲得できるという体験ができます。
また、ひらかたパークでは、SCRAPが提供するリアル潜入ゲームが人気で、最大3人でチームを組み、60分間で謎を解くスパイ体験ができます。
これらの体験型コンテンツは、「近畿地方のある場所について」が持つ「謎解き」の要素と親和性が高く、作品世界への没入感をさらに深める可能性を秘めていると思います。
この映画が提示する「謎解き」は、既存の謎解きゲームとは少し違ったタイプだと思います。それは、「既に与えられた断片的な情報をどう繋ぎ合わせるか」という、いわば「情報の再構築」の謎解きです。
現代社会において、膨大な情報の中から真実を見つけ出す能力は不可欠であり、この作品はエンターテインメントとして、その感覚を研ぎ澄ませる訓練にもなっているのではないでしょうか。
「実話なのか?」都市伝説と史実が交錯する境界線
映画「近畿地方のある場所について」は、そのモキュメンタリー形式と現実を連想させる描写から、多くの人が「実話なのではないか?」と疑問を抱きますが、公式には創作ホラー小説とされています。
その恐怖は、実在する場所の伝承や都市伝説を巧みに取り入れることで、真実味を帯びているのです。
モデルとなった場所や事件の可能性と「虚構」の線引き
本作の舞台は「近畿地方のある場所」とされており、特定の地名は伏せられています。しかし、その描写からは、関西各地に実在する心霊スポットや都市伝説がモデルになっていることがうかがえます。

最も有力なモデル地とされる滝畑ダムは、大阪府河内長野市に位置し、心霊スポットとして知られています。
小説の表紙に描かれた階段や祠の描写が、滝畑ダム周辺の実際の風景と一致すると指摘。
滝畑ダムのような山奥の場所と、鳥居や小道といった要素を組み合わせることで、心霊的な表現が生み出されています。
大阪の東部に広がる生駒山地も、作品世界を構成する重要な場所。
生駒山は古くからの信仰の対象であり、山中にある宝山寺(生駒の聖天さん)は商売繁盛や縁結びで有名ですが、「願いには代償が伴う」という恐ろしい伝承も存在します。
また、生駒山系一帯には、霊的な地点や神聖な場所が「異界の網」のように点在し、これらが見えない線で結ばれているという説まであります。私もこの話を聞いたとき、背中がゾクゾクッとしました。
大阪府内には、他にも数多くの都市伝説や心霊スポットが存在します。
咲洲コスモタワー(大阪市住之江区):かつて日本第3位の高さを誇ったビルですが、バブル期に開発された人工島「咲洲」にあり、再開発と中断が繰り返されたことから「未完の都市」の印象を持たれています。ここには「存在しない階に停止するエレベーター」や「無人ビルに響く足音」といった都市型心霊現象が語り継がれています。
大仙古墳(堺市堺区):世界遺産にも登録された巨大古墳で、太古の龍神が封じられているという伝承があります。周辺での不審火や事故が「龍の怒り」と恐れられるなど、「結界」としての機能を持つとされています。
堺市の大仙古墳(仁徳天皇陵)に来たぞ!
— 古墳にコーフン協会 (@kofun_ni_kohfun) November 23, 2024
でかい・・・、森ですな。 pic.twitter.com/EG2qXoaZ3H
土佐堀川(大阪市西区):江戸時代に物資運搬や処刑場送りの舟が多く通った川で、深夜になると「舟に乗った人影」が流れていくという話があります。スマートフォンで撮影しようとすると画面が真っ暗になることもあるそうです。
美原中学校の「階段の女」(堺市美原区):過去に教師が転倒死した階段で、夜間にヒール音が聞こえたり、警備員が足元だけの女性の霊を目撃するという噂があります。
服部緑地(豊中市):広大な緑地公園で、夜になると「家族の名前を呼ばれたり、知らない子どもの歌声が聞こえる」といったささやき声の噂があります。
モノレール沿線(摂津市・茨木市):人工構造物が古来の霊道や結界を乱すことで霊障が起こるとされ、高架下は「霊の溜まり場」とされることがあります。
安威川沿い(茨木市):雨の日に着物姿のすすり泣く女の霊が現れ、声をかけると消えて水たまりに白い足跡が残るという話があります。
八尾南駅の「未来を見る階段」(八尾市):特定の段差を上り下りすると、その晩に未来の出来事を見る夢を見るという都市伝説がSNSで拡散されています。
柏原市の「鬼塚」:古くから「鬼の墓」と呼ばれる巨石が存在します。

これらの伝承は、作品が「近畿各地の怪談や噂がベース」になっているという原作情報とも一致します。
作品が実在の場所や伝承を「触媒」のように使うことで、読者の心に「これは本当かもしれない」という疑念を植え付け、虚構の物語を現実の恐怖へと昇華させているのだと感じます。
人間は不確かな情報にこそ、最も深い恐怖を覚えるのかもしれませんね。
考察で深まる「謎」の多層性
「近畿地方のある場所について」の恐怖は、単一の現象ではありません。複数の怪異が複雑に絡み合い、時系列を超えて繋がっていくことで形成されています。
本日から公開の背筋『近畿地方のある場所について』
— 西山智則 (@AEvDyCJ28vrd8i7) August 8, 2025
断片の情報をパズルとして組み合わせる。呪いが増殖する現代の『リング』だが、文庫版は違う展開で2度楽しめる
山へ誘うもの(まさる、ましろさま、まっしろさん、UMAのホワイトマン)は、「ましろ」から「猿婿」の世界に繋がり、謎を膨らませる pic.twitter.com/7R6SiGCulx

作中に登場する主な怪異には、「山へ誘うモノ(まっしろさん)」「ジャンプ女(赤い女)」「そして了あきら」などが挙げられます。
これらは、祠と御神体の移動、呪文、人を使った誘導、そしてインターネットやSNSによる情報拡散といった形で連鎖していきます。
例えば、「関西軍曹」が、お札屋敷で畳の下の石を発見するというXの投稿もあります。そして、同年夏には、関西の大学生がドライブ中に石の周りを飛び跳ね呪文を唱える人々を目撃し、そのうちの一人がおかしくなるという体験も報告されています。
お札屋敷の本来の姿は石が和室の畳の下に置いてあってお札が壁にかなりの量貼られてたと考えられる
— けけー (@keke85123) April 3, 2023
それをお札はおそらく肝試しにきた人が、石は関西軍曹が持ち去った
一見屋敷に何かが封印されてたように思えるけどジャンプ女もあきらくんもまっしろさんも2011年以前からわりと活動できてる
作品ではダムでの死体発見(2011年8月18日)や、小学生女児への不審者による「山に連れて行ってあげる」という声かけ(2018年10月19日)、そしてスマホを向けて「山へ行きませんか」という声かけ(2020年5月27日)など、具体的な日付を伴う事件や不審者情報が時系列で示されています。
これらの断片的な情報が、作品内の怪異と結びついていく様は、読者にまるで未解決事件の真相を追っているかのような錯覚を与えます。
原作者の背筋氏は、自身の卒論テーマが「恐怖感情を相手に伝える」だったことを明かしており、その知見が作品に生かされていると語っています。
同じ出来事でも、伝え手によって見え方が全く変わるという点は、作品の核心にある「リアリティ」を生み出す要素です。
白石監督は「霊的な存在の理不尽さ、不条理さ」を「究極の暴力」と捉えており、それがホラーとしてしっくりくると感じているそうです。
興味深いことに、人間が作り出した道具が「呪物」と化すという話も作品の根底にあります。とある怪談で、日本刀が最も呪物が入りやすい道具であると語られています。
その理由は、日本刀がそもそも人を傷つける目的で作られたものであり、殺意や切られた人の念がこもりやすいためだと説明されます。これは、「物が怖い」というレベルを超え、人間の念や負の感情が物質に宿るという、より深い恐怖を示唆しています。
この作品は「謎解き」という行為自体が、私たちを物語の「呪い」へと引きずり込む罠になっている、と強く感じます。
まるで、好奇心という人間の本能が、作品世界への扉を開く鍵であり、同時に、そこから抜け出せなくなる檻でもあるかのように。この巧妙な仕掛けこそが、多くの読者や観客を魅了し、心から離れられない理由ではないでしょうか。
聖地巡礼の新たな形と地域活性化の可能性

映画「近畿地方のある場所について」は、そのミステリアスな「場所」の描写によって、新たなコンテンツツーリズムの形を生み出す可能性を秘めています。
たとえ公式に場所が明言されなくとも、ファンは自ら「聖地」を探し出し、そこを訪れることで作品世界を追体験するでしょう。
コンテンツツーリズムとしての「近畿地方のある場所について」
JTB総合研究所の観光統計によると、2025年5月の訪日外客数は3,693,300人(前年同月比+21.5%)となっています。このような観光需要の高まりの中で、コンテンツツーリズムはますます注目されています。
コンテンツツーリズムとは、アニメやマンガ、ゲームといった「コンテンツ」をきっかけとした旅行行動や、コンテンツに関わる観光全般を指します。
これは観光地を訪れるだけでなく、ファン自身が情報を収集し、共有し、時には観光地づくりにも積極的に関わる「クリエイティブ・ツーリズム」の側面も持ち合わせています。
例えば、アニメ聖地巡礼では、ファンがアニメを視聴し、該当地域を発見・特定して訪れる「開拓的アニメ聖地巡礼者」が存在します。
彼らがSNSやブログ、動画投稿サイトで情報を発信することで、その情報を用いて聖地を訪れる「追随型アニメ聖地巡礼者」が増え、最終的にはテレビニュースなどで聖地巡礼を知り訪れる「二次的アニメ聖地巡礼者」まで広がり、来訪者数が数万人規模になることもあります。
奈良県では、京都アニメーションのアニメ作品『境界の彼方』が奈良を舞台にしており、イベント「奈良燈花会」とコラボレーションしてキャラクターの等身大パネルを設置した事例もあります。
和歌山県では、「サマータイムレンダ」の舞台となった友ヶ島が聖地巡礼スポットとなり、メインキャラクターが「和歌山市アニメ観光大使」に任命されるまでになっています。
大阪府は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、道頓堀、通天閣といった主要コンテンツに観光客が集中し、市外への周遊が進んでいないという観光課題を抱えています。宿泊施設も市内に集中しているため、周辺地域へのアクセス改善や地元企業の観光への積極的な参画が求められています。
このような状況下で、「近畿地方のある場所について」のような、ミステリー要素が強い作品が地域の持つ「暗部」や「異界」といった潜在的な観光資源を掘り起こし、新たな観光需要を創出する可能性があります。
観光庁の「令和6年版観光白書」によると、2023年のインバウンド消費額は5兆3千億円に達し、コンテンツツーリズムは重要な観光戦略として位置づけられています。
特に、体験型コンテンツへの需要は年々高まっており、単純な観光地巡りから「参加型」「謎解き型」の観光へとシフトしているのが現状です。
この作品は「謎解き」という要素と結びつけることで、より広範な層にアピールできるのではないでしょうか。
例えば、作中に登場する具体的な地名や伝承をヒントに、ファンが自ら「封印された町」や「怪異の真相」を解き明かす体験型ゲームを開発するのです。これにより、単なる観光ではなく、知的な探求心を刺激する「ディープツーリズム」が生まれるかもしれません。
これは、既存の観光資源の「隙間」を埋めるような、ユニークな地域活性化に繋がるはずです。
まとめ:映画「近畿地方のある場所について」はどこ?
映画「近畿地方のある場所について」の舞台とされる「ある場所」は、公式には明言されていませんが、多くのファンや考察からは大阪府河内長野市にある滝畑ダムがそのモデルである可能性が極めて高いと見られています。
原作小説の表紙の描写と実際のダム周辺の風景が酷似していることが、その有力な根拠となっています。
作品が特定の地名を伏せるのは、実在地域への配慮、モキュメンタリーとしての演出効果、そしてファンによる考察を促す戦略的な意図があると考えられます。この「曖昧さ」こそが、作品の持つ独特な恐怖感を生み出す重要な要素となっているようです。
本作は、SNSやネット掲示板の書き込み、インタビューといった現代的な要素と、都市伝説や怪異の伝承を融合させたモキュメンタリーホラーです。
見る者に「実話なのでは?」と錯覚させるほどのリアリティを持っており、監督の白石晃士氏と主演の菅野美穂、赤楚衛二が作り出す映像と演技は、作品の持つ多層的な恐怖をさらに増幅。
撮影現場で実際に怪奇現象が続出したという裏話も、作品の持つ「呪い」の力を物語っているかのようです。この作品は、単なるホラー映画を超えて、情報社会における「見えない恐怖」や、好奇心によって引き込まれる「謎解き」体験を提供しています。
この作品が示すのは、現代における恐怖の新しい形です。インターネット時代の情報過多と心理的脆弱性を巧みに突き、物理的な場所の恐怖だけでなく、情報空間という「見えない場所」に潜む恐怖を描いている点が、真の怖さの源泉なのかもしれません。
覚えておきたいポイント
- 滝畑ダムは幽霊トンネル・自殺地
- 生駒山は修験道聖地・トンネル怪談
- 赤い女の霊は中津高架下等で目撃
- 大阪城は怪談多い日本一の城
- 通天閣地下に異界門や封印石
- 千里ニュータウンに消える住民の怪談
- 井戸は異界への入口・怪談の舞台
- 地下鉄駅や高架下、踏切は霊集まる
- 開発と信仰の衝突が怪異を生む
- 作品内要素が現実世界へ拡張する恐怖



