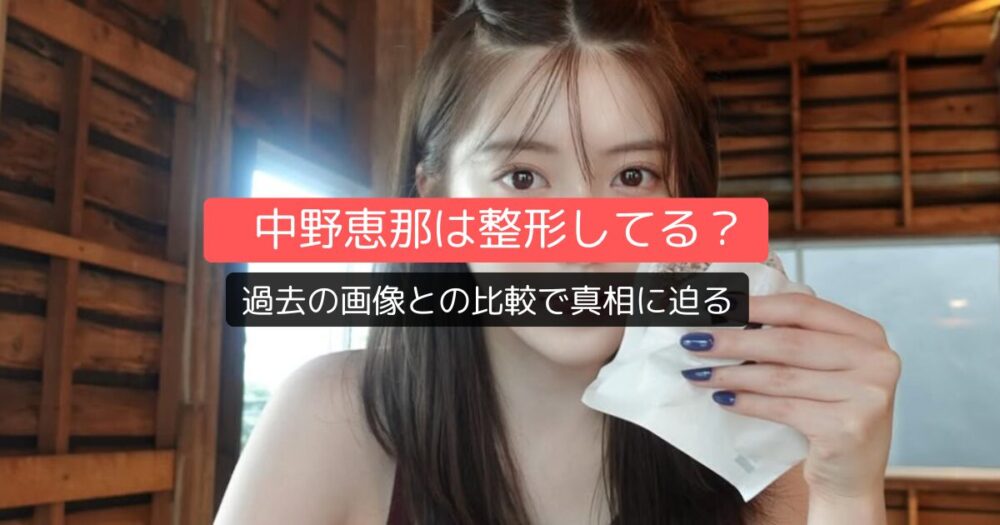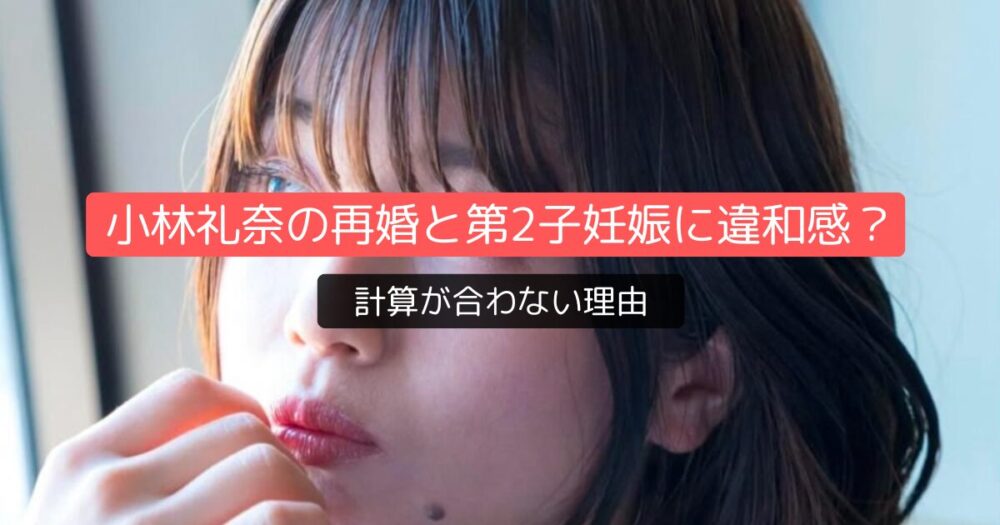「流暢さより伝わる力」高市早苗総理の英語力"Japan is back"に込められた真の実力と戦略
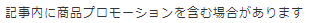

「英語が話せる政治家」と聞いて、あなたはどんな姿を思い浮かべるでしょうか。流暢にネイティブのように話す人物を想像するかもしれません。ですが、国際政治の現場で本当に求められるのは、むしろ別の能力です。高市早苗氏の英語力を巡る議論は、まさにその本質を浮き彫りにしています。
2025年9月27日、YouTube上で配信された「ひろゆきと語る夜」で起きた"事件"があります。
論破王として知られるひろゆき氏が、自民党総裁選の候補者5人に「日本をどんな国にしたいか、英語で1分間答えてください」と突然の無茶ぶりをしたのです。
林芳正氏と茂木敏充氏は英語で答えました。コロンビア大学院を修了した小泉進次郎氏は日本語を選びました。そして高市早苗氏は、「私の場合はもうワンフレーズ、"Japan is back"」とだけ英語で述べ、その後は日本語で政策を語ったのです。
この場面で高市氏は覚悟を決めた表情を見せ、短いフレーズの後に日本語での回答を続けました。SNS上では賛否両論が巻き起こりました。
「米議会で働いていたのにこの程度か」という批判もあれば、「正確に伝えることを優先した判断だ」という擁護も。だが、この討論会での対応だけで彼女の英語力を測ることはできません。なぜなら、国際会議の場での高市氏は、まったく異なる顔を見せているからです。
高市早苗総理の英語力:実戦で炸裂した「即応力」IAEA総会での衝撃シーン
高市早苗氏の真の英語力が注目されたのは、2023年にウィーンで開催された国際原子力機関(IAEA)第67回年次総会でのことです。
東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出後、初めての総会でした。国際社会の理解を求める重要な舞台だったのです。
準備された原稿を超えた瞬間
この総会で高市氏は、原稿にない中国への反論を急遽差し込み、即座に英語でスピーチを切り返しました。これは単なる棒読みではありません。抑揚をつけて堂々としたスピーチ力で聴衆を引き込んだといいます。
思わず息を呑みます。政治の世界で、こうした「瞬発力」こそが最も重要なのです。
事前に用意された美しい英語を読み上げることなら、誰にでもできます。だが、相手の主張を受けて、その場で英語の反論を構築できる政治家がどれだけいるでしょうか。
高市氏のスピーチ力は自分で考えた原稿内容をスピーチメモを見ながら話す力がかなり高く、読解力・ライティング力は大学院生かそれ以上のレベルと評価されています。これは米国での経験が確実に血肉となっている証拠でしょう。
米国議会での2年間が育てた実戦力
高市氏の英語力の土台を理解するには、若き日の経験を知る必要があります。1987年から2年間、高市氏は松下政経塾のスポンサーシップを受けてアメリカで「コングレッショナルフェロー」として働きました。
これは語学留学とは次元が違います。議会スタッフとして議員事務所で立法補佐官の業務に携わり、政府のあらゆる情報にアクセスできる環境に身を置いたのです。
高市氏はアメリカ民主党下院議員のパトリシア・シュローダー氏の個人事務所で勤務していました。シュローダー議員はアメリカ史上初の女性大統領候補を目指していたやり手の政治家です。

わたしが注目するのは、この経験が持つ意味の深さです。
教室で学ぶ英語と、議会で法案作成や公聴会準備をする英語は全く別物なのです。専門用語が飛び交い、論理的な議論を瞬時に理解し、反論を構築する。高市氏は月2000ドルの研究費を受け取りながら有給で仕事をしていた記録も残されています。
つまり、これは正式な職務だったのです。
「流暢さ」より「伝わる力」戦略的言語運用という武器
「高市早苗 英語力」と検索すると、評価は真っ二つに割れます。「発音がネイティブレベルではない」という指摘もあれば、「実務に十分通用する」という評価も。だが、この議論自体が本質を見失っているのではないでしょうか。
英語力イメージ調査が示す意外な結果
トライズ社が実施した調査(18歳〜59歳の1008人対象)で、自民党総裁選候補者5名の中で「最も英語を話せるイメージがある人物」を尋ねたところ、高市早苗氏が13.2%で最多となりました。小泉進次郎氏(12.9%)を僅差で上回る結果です。
さらに興味深いのは、「トランプ米大統領と交渉等が最もできそうなイメージを持つ人物」では、高市早苗氏が20.3%でダントツのトップとなった点です。小泉氏(9.6%)、茂木氏(6.6%)を大きく引き離しています。
この数字が物語るのは何でしょうか。有権者は「英語の流暢さ」よりも「交渉力」を重視しているということです。わたしはここに、現代の政治家に求められる本質を見ます。
3つの「型」から見る政治家の英語
高市早苗氏の英語は、ネイティブのような滑らかさよりも実務に役立つ現場型の英語と評されています。
討論会では短く印象的なフレーズを強調し、スピーチでは準備した原稿を明瞭に読み上げるスタイルで、これは政治的メッセージを的確に届けるための戦略的な言語運用なのです。
他の政治家と比較してみましょう。
| 政治家 | 英語の特徴 | 強み |
|---|---|---|
| 林芳正 | ハーバード大学院出身、流暢で洗練された英語 | 文法・発音の完成度 |
| 茂木敏充 | 外交経験豊富、フォーマルで正確な英語 | 国際会議での安定感 |
| 高市早苗 | 米議会経験、戦略的で実務志向の英語 | 即応力と説得力 |
「Japan is back」というフレーズを選んだのも、実は深い戦略があります。安倍晋三元首相が使った象徴的なメッセージを引き継ぎ、短く力強く印象づける。討論会という限られた時間の中で、最も効果的な「一撃」を放ったとも言えるのではないでしょうか。
「経歴詐称疑惑」の真相|コングレッショナルフェローとは何だったのか
高市氏の英語力を語る上で避けて通れないのが、米国議会での経歴を巡る論争です。
高市氏が初期に名乗っていた「米連邦議会立法調査官」という肩書きについて、コングレッショナルフェローの直接的な訳語は「議会特別研究員」であるという指摘があります。
ひろゆき氏が投げかけた疑問
2025年8月、ひろゆき氏がXで「高市早苗さんが『米連邦議会立法調査官』と名乗ってる画像。アメリカ国籍しか公務員になれないから、画像が正しいなら高市早苗さんはアメリカ二重国籍か経歴詐称?」と投稿し、話題となりました。
実際はどうなのでしょうか。パトリシア・シュローダー議員のサインによる証明や、アメリカ議会のCRS(コングレッショナル・リサーチ・サービス)によるコングレッショナルフェローの裏付け資料、そして月2000ドルの送金記録も残されています。

つまり、高市氏が米国議会で実際に働いていたことは事実なのです。
問題は「肩書きの日本語訳」にあります。思うに、これは35年以上前の若き日の表現を、現代の厳密な基準で裁く難しさを示しているのです。当時は適切と思われた訳語が、時代とともに精査されるようになりました。
重要なのは、彼女が実際に米議会で働き、そこで英語力を磨いたという事実でしょう。
第三者の声「経歴より実力を見るべき」
SNS上では様々な意見が飛び交っています。「経歴を盛りすぎでは」という批判もあれば、「30年以上前のことを今さら」という声も。
ある政治評論家はこう語ります。「肩書きの翻訳の問題よりも、実際に国際会議で成果を出せるかどうかが重要だ」。
実際、調査では英語力ある政治家を「頼もしいと思う」と答えた人が64.2%に上り、総裁選候補者に英語力が大事だと思う人は66.8%に達しました。
有権者が求めているのは、過去の肩書きではなく、今そこにある実力なのです。
国際舞台で戦える「リーダーの資質」とは何か
高市早苗氏の英語力を巡る議論から見えてくるのは、現代の政治家に求められる能力の本質です。
SNSの声と専門家の評価
英語専門家は「高市氏の英語力と海外との英語によるコミュニケーション力だけを見ると、近年にないくらい期待して良い」と評価しています。
一方でSNSでは「米議会で働いていた割にもっと話せるはずでは?」といった厳しい声も散見され、期待値の高さゆえに評価が割れるのが現実です。
トランプ時代の外交に必要な力
外交の現場では「語学力」以上に「瞬発力と説得力」が問われます。相手の意表を突くような場面で即応する力。これこそが、今の時代のリーダーに不可欠な資質です。
高市氏が「Japan is back」とだけ言って日本語に切り替えたのは、弱さではなく選択だったのかもしれません。
1分という時間で何を伝えるべきか。完璧な英語で抽象的な理想を語るより、日本語で具体的な政策を正確に伝える方が有権者のためになる。そんな判断があったとしたら、それは戦略的思考の表れです。
まとめ:高市早苗氏の英語力「伝わる英語」こそが真の武器
高市早苗氏の英語力は、流暢さではなく「実戦力」にあります。米国議会での2年間、IAEA総会での即興対応、そして戦略的な言葉の選択。
これらすべてが示すのは、「ネイティブのように話す」ことではなく、「相手の心に届き、交渉で成果を出せる」英語の持ち主だということです。
政治家の英語力を評価する時、私たちは何を基準にすべきでしょうか。発音の美しさでしょうか、文法の正確さでしょうか。それとも、国益を守り、国際社会で日本の立場を主張できる力でしょうか。答えは明白でしょう。
調査で「トランプ米大統領と交渉等が最もできそう」として高市氏がトップに選ばれた事実は、多くの人が本質を見抜いている証拠です。これからの日本に必要なのは、教科書的な英語ではなく、戦える英語を持つリーダーなのですから。
「Japan is back」。この短いフレーズに込められていたのは、挑戦と覚悟だったのかもしれません。高市早苗氏の英語力を巡る議論は、私たちに問いかけています。あなたは政治家に、どんな言葉の力を求めますか?
参考情報